雪国は川端康成の代表する小説である。
主人公は既婚の身であるにもかかわらず、無為に一人旅を続ける男、島村である。島村は、ある雪国で駒子という女性と出会い、翌年再会するために乗った汽車の中から物語が始まる。汽車の中で島村は再び葉子という女性と出会う。葉子は病弱な男を連れており、甲斐甲斐しく看病しているようだ。
葉子が看病していた男は行男と言い、間も無く死を迎えることがわかっている。行男は葉子にとって大切な人であることは汽車の描写でも明らかだが、話が進むにつれ、実は駒子も行男の療養費を稼ぐために芸者になったことを島村は知る。
駒子と葉子は共に生活しているようだが、お互いの関係については謎に包まれている。しかし、その間には何か、かつて男女のいさかいめいたことが静かに行われていたことを匂わせている。結局、物語の中では語られないまま話は終わるが、二人の関係を文脈から想像することは、この物語を紐解くための肝だと思われるため、今回はその点を掘り下げてみたい。
駒子と葉子について
駒子と葉子の二人の女性について、まず触れておきたい。
駒子の人柄を表すキーワードとして「清潔」「徒労」「真面目」がある。島村は駒子のことをこう表現している。
“女の印象は不思議なくらい清潔であった。”
“鏡の奥が真白に光っているのは雪である。その雪の中に女の真赤な頬が浮かんでいる。なんともいえぬ清潔な美しさであった。”
“蚕のように駒子も透明な体でここに住んでいるかと思われた。”
駒子はとても純粋であることがわかる。当初、島村は駒子に別の女を紹介してくれないかと無礼な要求をするが、それは駒子が純粋すぎるために手を出すのを躊躇ったからである。駒子は次第に島村に魅かれ、周りの目も顧みず時間を見つけては島村に会いに行こうとする。しかし、既婚者である島村とこのままの関係を続けられないことも駒子は理解しており、それによってやがて身も心も蝕まれてしまうのだ。島村はそんな駒子が突き進む「徒労」を見て、なお一層の純粋さを感じ魅かれていくのであった。
一方、葉子は「真剣」「刺すような目」が主なキーワードとして用いられている。特に、
“悲しいほど美しい声だった”
という表現は度々用いられており、非常に印象的だ。
葉子は、情事を重ねる島村と駒子の様子を遠目から眺めているが、その本心は見えにくい。行男の容体が悪化したことを葉子が駒子に急いで伝えにくるシーンでは、
“葉子は呆然としゃっちょこ張って、駒子を見つめていた。しかし顔つきは余りに真剣なので、怒っているのか、悲しんでいるのか、それが現われず、なにか仮面じみて、ひどく単純に見えた。”
とある。葉子はいつも真剣であり、何らかの強い情念に取り憑かれたように生きている。それが「ひどく単純に見えた」という表現の中に集約されている。結局、駒子は行男の死に目を見ることを拒む訳であるが、そこにも二人の間には大きな“しこり”があるように思われる。この“しこり”が何であるかは最後まで明らかにはならない。
“駒子の愛情は彼に向けられたものであるにもかかわらず、それを美しい徒労であるかのように思う彼自身の虚しさがあって、けれども返ってそれにつれて、駒子の生きようとしている命が肌のように触れて来もするのだった。彼は駒子を哀れみながら、自らを哀れんだ。そのような無心に刺し通す光に似た目が、葉子にはありそうな気がして、島村はこの女にも惹かれるのだった。”
おそらく、島村は駒子との関係がやがて破滅へ進む道であることをわかっており、その罪悪感を見透かすような葉子に、畏れにも似た魅力をいただいているのではないか。
なぜ、葉子は泣いたのか
終盤に差し掛かるところ、島村と葉子がほぼ唯一の会話をするシーンがある。その会話は次のように終了する。
“「駒ちゃんをよくしてあげて下さい。」
「僕にはなんにもしてやれないんだよ。」
葉子の目頭に涙が溢れて来ると、畳に落ちていた小さい蛾を掴んで泣きじゃくりながら、
「駒ちゃんは私が気ちがいになると言うんです。」と、ふっと部屋を出て行ってしまった。
島村は寒気がした。”
急な展開なため、読者はすぐに葉子の行動の理由が掴めない。なぜ、葉子は泣いたのだろうか。
島村は駒子と知り合ってしばらく経った頃、町の噂で駒子が行男の許嫁であったこと、行男の療養費を稼ぐために駒子は芸者の道に進んだことを知る。駒子にそのことを問うてみても、行男とは何にもなかったのだと否定をする。行男の容体が悪化しても駆けつけず、行男の墓参りにも行かない駒子をみて、島村は腑に落ちない思いを持つ。
本当に駒子は行男と何もなかったのだろうか。いや、そんなことはない。駒子が初めて東京に行く際に唯一見送ってくれたのが行男であったと、駒子の日記の冒頭に書かれている通り、駒子にとって行男は特別な存在であったのは明らかだ。しかし、葉子が現れたことによって状況は一変したと考えられる。いつも真剣な葉子の行男への想いを目の当たりにし、自分が身を引くことを余儀なくされたのではないだろうか。駒子が旅人である島村に夢中になったのは、その空いた心を埋めるためであったのかもしれない。
一方、葉子は駒子の大事な人を奪ってしまった負い目をずっと感じていたのではないだろうか。島村との会話では
“「駒ちゃんをよくしてあげて下さい。」”
という台詞と共に
“「駒ちゃんは憎いから言わないんです」”
とも発している。おそらく葉子の中には駒子への負い目と、恋敵であった憎しみ、二つの矛盾した感情が渦巻いているのだろう。島村に東京に連れて行ってほしいなどと頼む理由は、その苦しみから逃れたいためではないか。
行男が死んで1年が経とうというのに、葉子は毎日墓参りをしている。おそらく、かつて看護師になるために東京へ住んだのも、行男の面倒を見るためだったのだろう。やがて死にゆく運命にある相手に向けるその想いは「徒労」の他にない。駒子が島村を想う「徒労」と、かつて自分が行男に向けていた「徒労」が重なるのである。島村と駒子に向けられる葉子の「刺すような目」は、葉子のそういった思い故ではないだろうか。
葉子が泣いた理由。それは、島村が駒子に何もしてやれないという耐え難い事実が、かつての自分と重なり絶望にも似た思いから来るものではないか。「駒ちゃんは私が気ちがいになると言うんです。」というそれは、苦しみの淵にいる葉子を、駒子が案じてかけた言葉ではないか。その駒子の気遣いが、葉子をなお一層苦しめているのだ。
クライマックスの美しさ
川端康成の文章は、情景の美しい表現にその真骨頂が現れる。
物語終盤、火事が起こり騒ぎとなる。火元である繭蔵に向かって走る島村と駒子は、冷たい風を切ることで流れる涙によって、空の天の川が滲む。その情景の美しさもさることながら、「天の川」という単語があの七夕伝説を想起させ、やがて終わりを告げる二人の関係を暗示するのだ。
最後、炎の中から瀕死の葉子が姿を現す。それを見た駒子は島村の側から飛び出す。
“葉子を胸に抱えて戻ろうとした。その必死に踏ん張った顔の下に、葉子の昇天しそうにうつろな顔が垂れていた。駒子は自分の犠牲か刑罰かを抱いているように見えた。”
「犠牲」や「刑罰」といった言葉が実に虚しく、報われない現実を突きつけている。
葉子の頭上には、炎が灯火となって揺らめいている。それは物語冒頭、汽車の中で窓に映る葉子と、窓の奥に見える夕日が重なり、灯火のように見えた光景を思い起こさせる。そして最後は下記の文で締め括られる。
“「この子、気がちがうわ、気がちがうわ。」
そう言う声がもの狂わしい駒子に島村は近づこうとして、葉子を駒子から抱きとろうとする男達に押されてよろめいた。踏みこたえて目を上げた途端、さあと音を立てて天の河が島村のなかへ流れ落ちるようであった。”
島村は何もすることができず、ただ傍観しているしかないのだ。

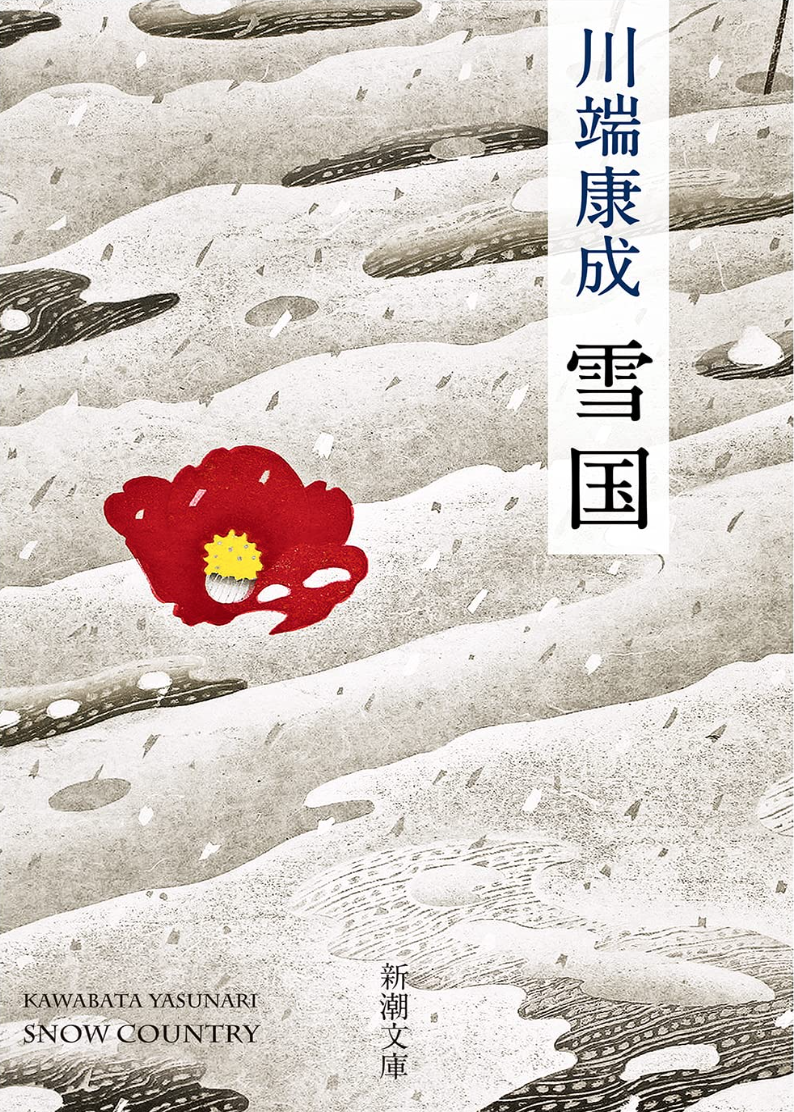
コメント